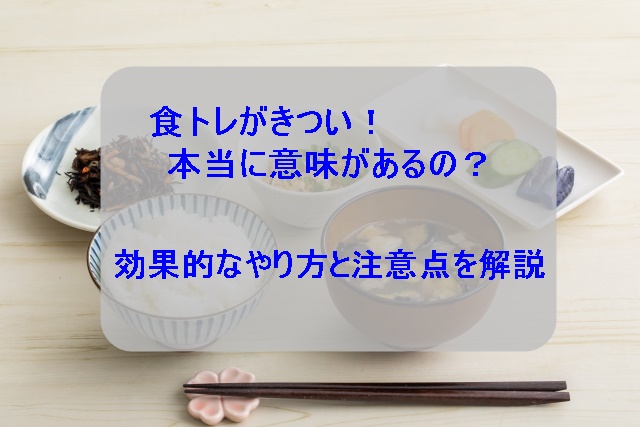食トレはスポーツでのパフォーマンスを上げるために食事量や内容をコントロールすることです。
ところが「身体を大きくするために、たくさん食べなければいけない」と思って、無理やり食べるように指示するケースがあるようです。
その結果、「食トレがきつい」「食トレに意味なんか、ないのでは?」と疑問に感じる選手や保護者の方がいらっしゃるのではないでしょうか?
食トレは次のような方法で行うと効果があると言われています。
- 目標を決める
- 専門家のアドバイスを受ける
- 選手自身が納得して取り組む
これらができていないと、食トレが苦痛になり「きつい」「意味がない」と感じてしまいます。
このページでは、食トレがきついと感じる理由やメリット・デメリット、成功例と失敗例などを交えて詳しくご説明しています。
スポンサーリンク
食トレ(食事トレーニング)の意味は?

食トレは、食事の内容や量を調整して体型の改善やパフォーマンス向上を目指すために行うトレーニングの種類です。
「食事トレーニング」を略して「食トレ」と呼ばれています。
食トレの意味と目的
食トレの意味や目的としては、次の4つがあげられます。
- 筋力UPと筋肉の修復
- パフォーマンスの向上につながる
- スタミナがつく
- ケガや病気の予防につながる
では、ひとつずつ説明していきます。
筋力UPと筋肉の修復
良質なたんぱく質を適切な量で摂取することで、トレーニング後の筋肉の修復をサポートできます。
また、バランスのいい食事を摂ることで身体に必要な筋肉量や体脂肪率を維持することができます。
パフォーマンスの向上につながる
運動前・運動中・運動後などそれぞれ適切なタイミングで必要な栄養素を摂取することで、パフォーマンスの向上につながります。
スタミナがつく
しっかり食べることで、試合が終わるまで体力を維持できるようになります。
途中でバテたりしないためにも、スタミナをつけることが大切です。
ケガや病気の予防につながる
食トレで筋肉や体力がついてくると、ケガをしにくくなります。
食トレと合わせて運動、柔軟体操などで強い筋肉やしなやかな身体を作ることで、ケガの予防につながります。
また、栄養バランスのいい食事を摂ることで、免疫力がUPし、病気予防にもつながっていきます。
食トレのメリットとデメリット
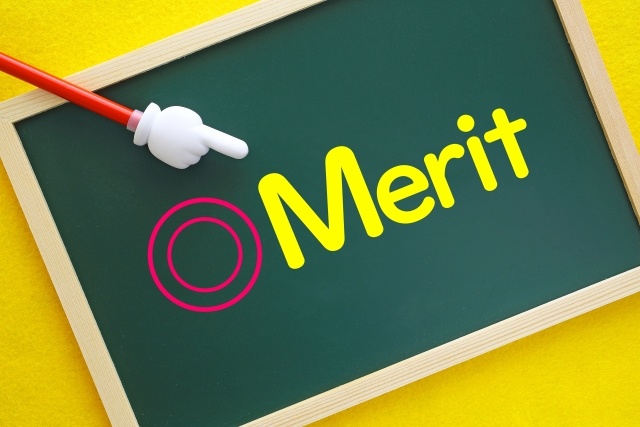
食トレにはメリットとデメリットがあります。
食トレのメリット
食トレのメリットは上に書いたように、筋肉やスタミナをUPさせて、運動のパフォーマンスを上げることができます。
食トレを実施する前ではできなかったことが食トレで身体が大きくなったために可能になると、試合で成果が出るだけでなく自分の自信にもつながっていきます。
食トレのデメリット
一方、食トレのデメリットとしては、その目的は意味を理解していないと「きつい」と苦痛に感じてしまうことです。
「どうしてもこれ以上食べられない」「でも、食べないと叱られる」の悪循環で、次第に食べること自体が苦しくなってしまい、取り組んでいたスポーツそのものに嫌悪感を抱くことにもなりかねません。
また、監督やコーチの指示に従わないことで、「自分はダメな人間だ」と劣等感を感じたり、スポーツでの成果が出ないときに「食トレ」を忠実にしなかったからだと自分を責めたりしがちです。
食トレが「きつい」「意味ない」と感じる理由
食トレはスポーツのパフォーマンスをUPさせるという点では、とても意義のあるものですが、中には「きつい」とか「意味がないのでは?」と感じる人もいます。
その理由を探ってみましょう。
食トレがきつい理由
量にだけ着目すると、それだけの量が食べられない人は「きつい」と感じてしまいます。
好き嫌いがある場合も同様で、嫌いなものを無理やり食べなきゃいけないときは「きつい」と感じてしまいます。
「どうしても食べられない」というときはそれに代わる食材を用意するなどの配慮が必要でしょう。
また、逆に甘いものやおやつが好きな人が、それを禁止されるときも「つらい」と感じてしまいます。
食トレが意味ないと感じる理由
食トレは即効性がありません。
そのため、最初はたくさん食べるだけで苦しい思いをするために「これが何の役に立つのだろう」と疑問を感じてしまいます。
特に食べることが苦痛になっていると、「食トレなんか、意味がない」と思ってしまうのです。
食トレの成功例と失敗例

次に食トレの成功例と失敗例を見ていきましょう。
食トレの成功例
食トレの成功例は多くのスポーツで見られます。
例えば、今アメリカのメジャーリーグで活躍している大谷翔平選手は、身長193cm、体重は95Kg(※)ですが、中学校時代は小柄だったそうです。
(※参考:侍ジャパンオフィシャルサイト)
しかし、成長期ということもあり、中学校時代に身長は20㎝伸び、さらに花巻東高校時代には1日にどんぶり飯10杯食べるという食トレを行ったことで、高校3年間で体重が20Kg近く増えたと言われています。
もちろん食トレだけでなく、きちんとした指導のもとで筋トレなどの運動も取り入れた成果だと言えるでしょう。
また、メジャーリーグに行ってからも身体作りに余念がなく、すばらしいパフォーマンスを上げています。
食トレの失敗例
無理やり食べさせることで、選手自身が苦痛に感じることはよくあります。
特に「米を毎食2合」とか「どんぶり飯を毎食10杯」とか、やみくもに量だけに注目した食トレは苦痛に感じてしまいます。
いくつかの例を挙げてみましょう。
「先輩やコーチが見張っているので、食べられなくても残せない」
といった不安から、その競技をやめてしまった。
「たんぱく質をたくさん摂るのがいい」と聞いたので、毎日大量の卵を食べた結果、血液検査の数値が上がってしまった。
栄養士など専門家の指示に従った食トレでないと、栄養バランスが崩れ、体調を悪化することにもなりかねません。
食トレが失敗する原因
食トレが失敗する原因としては、指導者が「とにかくたくさん食べることが大切」と信じていることや「食べる量にだけこだわって、栄養バランスや食べるタイミングを考えていないこと」などがあります。
また、選手のメンタル面に配慮していないと、自信喪失や自己嫌悪に陥ってしまうこともあります。
メンタルでダメージを受けると、競技の成績にも悪い影響を及ぼすだけに配慮が欠かせません。
スポンサーリンク
食トレが健康に与える影響

スポーツで成果を上げるために取り組んだ食トレのせいで、健康面でマイナスの影響を受けることがあります。
食トレで健康面が悪化
食トレにばかり意識が向いてしまい、筋トレなどがおろそかになると体重が増加するだけになってしまいます。
上でも書いたように栄養バランスが悪いと、血液検査などの数値に悪い結果が出ることがあります。
逆に健康面で悪影響が出るので注意が必要です。
食トレで吐く
無理やり食べたはいいけれど、後で吐いてしまう……というケースがあります。
また、そんな自分はダメなんだ…と自分で自分を追い込んでしまう選手もいます。
食トレがメンタルに与える影響
スポーツをする人に限らず、本来食事は楽しみなものです。
ところが食トレがあるために、「また食べなきゃいけない」と気が滅入ってしまうことがあります。
さらに下級生が食べているのに、上級生の自分が食べないわけにはいかないと無理やり食べて、苦しむということもあります。
その結果、食事がイヤになり、その競技自体も嫌いになる可能性もあります。
食トレでチームの関係が悪化
合宿や寮生活をしていると、たくさん食べる人がもてはやされたり、褒められたりします。
また、食べないと監督の機嫌が悪くなるので、イヤでも食べる…という選手もいます。
しかし、監督やチームメイトとの関係が悪化すると、パフォーマンスの低下につながってしまうでしょう。
また、そのスポーツから離れてしまう人もいます。
食トレの効果的なやり方と注意点

最後に食トレの効果的なやり方と注意点をご紹介します。
食トレの効果的なやり方
むやみに「たくさん食べろ」と強要したり、「勝ちたいなら食べろ」といった「根性論」は避けるべきです。
栄養バランスを考慮していない食トレは、選手がメンタル面で追い込まれてしまいます。
そのためには効果的な方法を知ることが大切です。
流れとしては、次の点を意識してみましょう。
- 目標を決める
- そのためには何をどれだけ食べればいいのか、専門家のアドバイスを受ける
- 選手自身が納得して取り組む
① 目標を決める
食トレは1日や2日で成果が出るものではありません。
特に「来シーズンの試合で〇〇の結果を出そう」という場合は、かなり長期にわたって取り組むことになります。
その際に挫折しないためにも、目標をしっかり決めて、モチベーションを維持できるようにすることが大切です。
② 専門家のアドバイスを受ける
食トレは食事に関することであり、健康面にも大きな影響を与えます。
特に成長期の選手は栄養のバランスが偏らないように配慮する必要があります。
そのためにもスポーツに詳しい栄養士のアドバイスを仰ぐことが大切です。
また、自宅で食事を摂る場合は、保護者にも説明して理解を得るようにしましょう。
③ 選手自身が納得して取り組む
食トレは無理強いしてもうまくいきません。
特に今の時代は根性論を全面に出しても、選手は動かないでしょう。
それよりも、きちんと理論的に説明して選手自身が納得して取り組めるようにすることが大切です。
また、一度にたくさんは食べられなくても、小分けにして食べるとか、〇〇は苦手だけど代わりに△△なら食べられるといった配慮をしてあげると、無理なく取り組めます。
選手自身もその方が納得して取り組めるのではないでしょうか。
食トレの注意点
食トレは選手のメンタル面や健康面にプラスになるように取り組む必要があります。
食トレをすることで気持ちが落ち込んだり、競技がイヤになって辞めてしまうことのないように配慮してあげましょう。
また、目標に合った内容で取り組むことが重要です。
競技ごとにどの栄養素をどのタイミングでどれだけ摂取するのがいいのか、また、選手一人ひとりの体調なども考慮してメニューを考えてあげるといいでしょう。
決して食べることを強要するのではなく、「何のためにこれを食べるのか」といった意味や目的意識を持つことが大切だと言えます。
まとめ
今は食トレはスポーツ選手にとってはなくてはならないものになっています。
プロ選手、アマチュア選手を問わず栄養やサプリメントのことなど選手自身もさまざまな知識を取り入れています。
ただ、指導者の中には「食トレ」=「たくさん食べること」と思い込んで、とにかく量を食べさせようとする人がいるようです。
食トレはバランスよく食べて身体を作り、同時に効果的なトレーニングをすることで競技のパフォーマンスを上げるということをしっかり理解しておきましょう。
根性論に走ることなく、科学的に正しい知識を取り入れて、成果の出る食トレを実践してみましょう。
スポンサーリンク